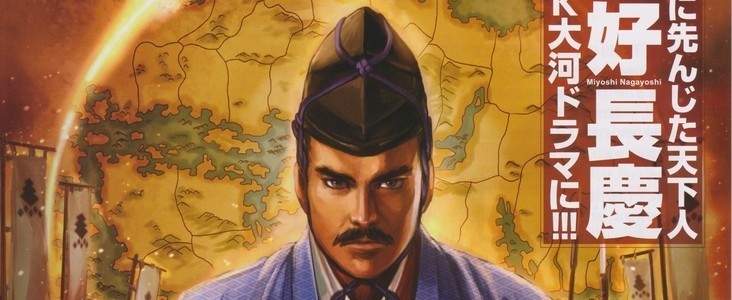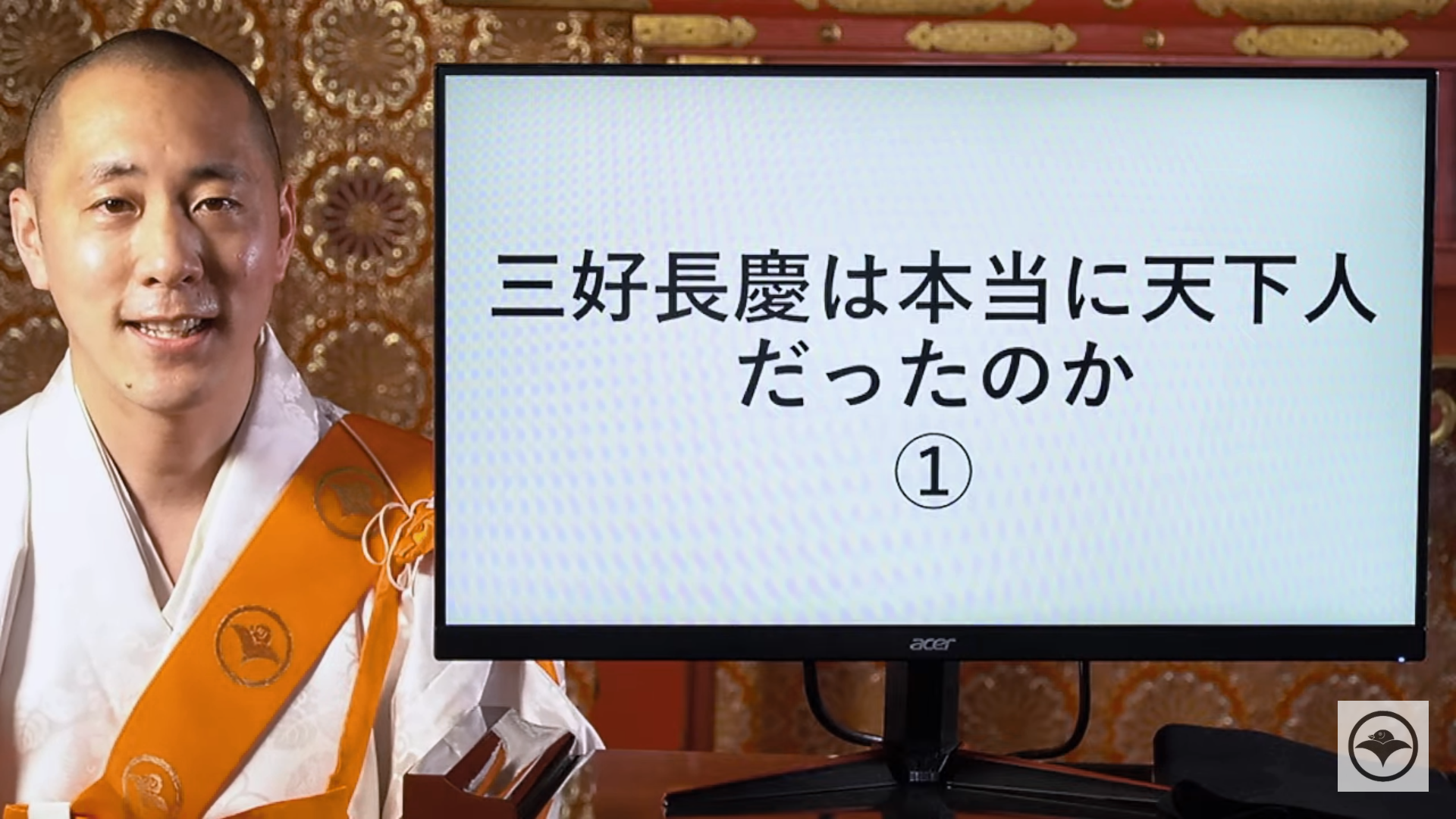顕本寺とは~寄り添いのトータルサポート
大阪府堺市に佇む、法華宗(本門流)の寺院・顕本寺。室町時代に日隆聖人によって建てられたこの寺院は、約570年に亘り「南無妙法蓮華経の教え」を伝え続け、今日に至るまで多くの皆様の生活や人生に寄り添ってきました。令和の時代になってもその姿勢は変わりません。「寄り添いのトータルサポート」。これを実践し続けて参ります。また570年の歴史上、様々な人物との関りがあります。境内には戦国武将・三好元長や、戦国時代の流行歌を作った高三隆達の墓所等があります。
もし仏事に関するご相談がございましたら、
お気軽にお問合せ下さい。
常住山 顕本寺(けんぽんじ)
(ご相談の方は下記をタップ)
072-232-3964